【今日の歌】誰にも見せない絵描きさん ― 2021/01/03
【今日の歌】誰にも見せない絵描きさん
シャンソン
誰にも見せない絵描きさん
ひとりで歌う歌うたい
当選できない政治家さん
るんるる~ るんるん~
勲章もたない兵隊さん
星なんかつかない料理人
論文書かない学者さん
らんらら~ らんらん~
君達どこかの星なのか
何を食べて生きてるの
そこじゃあ寒くはないのかね
ふんふ〜ん ふふふんふん
僕もそんな仲間かな
できたとたんに忘れちゃう
詩人なのにだまってる
しゃんしゃしゃ〜ん しゃんしゃさん
星の下には大地があって
歌も言葉も、そこの下
仲間はみんな、わかってる
るんるる~ るんるん~
作詞 ジャン・ルダン
曲 ジュエル・サドニダン
訳詞 森谷昭一
秘密の図書館蔵書より
曲は三拍子でちんどん屋風な演奏です
シャンソン
誰にも見せない絵描きさん
ひとりで歌う歌うたい
当選できない政治家さん
るんるる~ るんるん~
勲章もたない兵隊さん
星なんかつかない料理人
論文書かない学者さん
らんらら~ らんらん~
君達どこかの星なのか
何を食べて生きてるの
そこじゃあ寒くはないのかね
ふんふ〜ん ふふふんふん
僕もそんな仲間かな
できたとたんに忘れちゃう
詩人なのにだまってる
しゃんしゃしゃ〜ん しゃんしゃさん
星の下には大地があって
歌も言葉も、そこの下
仲間はみんな、わかってる
るんるる~ るんるん~
作詞 ジャン・ルダン
曲 ジュエル・サドニダン
訳詞 森谷昭一
秘密の図書館蔵書より
曲は三拍子でちんどん屋風な演奏です
今日の詩「三色の春の」 ― 2012/03/30
三色の春の丘の声
丘は三色に染まり、春
レンギョウ、 緋の桃 、豆桜
柔和な土の香、里の丘
あなたが笑顔で
手を振るしぐさ
まっすぐ私をみつめる眼
花によろび
花とあそぶあなた
何もかも今ここにとどまる
こんな近くに丘があり
こんな近くに花があり
こんな近くにあなたがいる
幸せ満ちる一度の春
ふたたび戻らぬ輝きよ
永遠に花咲く里の丘
丘をおとづれる恋人達よ
毎春、われらは美をくりかえす
あたた達は美に向かい、通り過ぎる
いちどの春を過ぎゆく存在を
春を繰り返す存在がよびかける
むせる三色の春のいのち
花は、乙女に言葉を贈る
毎春ごとに美を得る幸せと
遠くへ消えぬ寂しさ語り
こんな近くに丘があり
こんな近くにあなたがいて
こんな近くに春がとどまる
丘は知る 花は知る
愛し合うもの達が
いつか風に、分かれていくことを
だから、消えゆくものへの
思いを光ににつつみ
丘は花を風にゆらす
丘を発ち、わきたつ夏にむかい
異なる街と空を求めて
旅に出るふたり
強い嵐が二人を引き離し
春の輝きはもう遠く
ふたりに、花の言葉は聞こえない
大きな声で呼び合い
過ぎゆく命の実りを得たら
旅の末にもう一度訪れなさい
こんな近くに丘があり
三色の春に輝きがあったことを
私たちが忘れない
こんな近くに花があり
こんな近くに涙して
こんな遠くに愛があり
切断面の響き 「水滴集」より
【読み】 香(か) 三色(みいろ) 永遠 (とわ)
毎春(まいはる)
【解説 1 】
この詩は、三 という数を基底として構成されています。三色の花 「こんな近くに」と言うリフレインをもった部分。3拍をきざむ形は、日本語ではあまり多くありません。
四行詩が、どこか安定感を持つのに対し、三という繰り返し形式は、どこか遠くに進んでいく流れを生み出します。一時の春の花を通り過ぎ、分かれていく運命にある恋人達を語るのに選ばれた形式なのでしょうか。
文頭が一文字下がって書かれいる節は、花の言葉です。詩は、花が恋人達にに語る形式をとってます。
レンギョウ、桃、豆桜 が揃って咲いているのは、関東では見慣れた風景です。そんな三色の花が、少し小高い丘の果樹畑を、たなびくように染めるます。身近で、のどかな風景です。
花の中で、出会い、語り合い、そして見つめる故に分かれていく恋人達。その儚い存在に、花が永遠を語りかけると言う構成で作られています。
「こんな近くに」の部分は、定型詩としてリズムをもって読んでください。情景描写の部分などは、少し破格で語りのリズムで読んでくだい。いずれにしても、声に出して読む事を前提につくられている詩です。
【鑑賞 2 】
恋人達が春の花満開の丘を手を握りあい歩きます。それは喜ばしい風景であるとともに、あやうい儚さも感じさせます。
花は彼らを祝福して語りかけます。でも恋する者には、その声は聞こえません。乙女の視線は、まっすく愛する者に向かい、その近しさの喜びに満たされ、そして「こんな近くに・・」と言う言葉を、たたみ込むように繰り返させます。
「忘れないでいる。」と言うのは、恋する者達どうし、良くささやかれる言葉ですが、その恋人達を、どこかでみつめる、花という存在がどこかにあると詩人は語っているのです。愛の成就には、花と語るやさしさと、永遠と語る強さが必要なのでしょう。
【鑑賞 2 】
思い出します。春の野で、恋人と、歩いた事を。こんな近しい、こんな満たされているとの思いに溢れていました。そして故郷の春は輝いていました。でも、見つめすぎたのかもしれません。やがて、遠くに憧れ、視線がいつしかずれていきました。
今から思えば、花の声を聞くこともなく、その幸せを感謝することもありませんでした。花の声が聞こえないで、人を愛せる筈もないのに。
いつしか、どこか私を包み、受け入れてくれる場所を探す旅に、人生が変わりました。沢山の人と出会い、また別れました。でも、あの春の輝きは見つかりません。
そして、春に故郷に戻り、ふと花咲く風景に会いました。花のもとに行ってみました。なにか、あの人にまた会える気がして。春の光が静かに、花に届いていました。けれど、そんな奇跡はあるはずもありません。
でも、今はこうして、花の声が聞こえるようになりました。木々や、風や、春の光と言葉を交わせるようになりました。永遠に触れた気が少しだけします。今なら、きっと誰かを本当に愛する事が出来る気がします。
【鑑賞 3 】
花が語ると言う思想はロマン主義の伝統です。花は永遠の象徴であると共に、消えゆく実存の象徴でもあります。永遠なる存在と、消えゆく存在の間での語りあいこそ愛の本質なのだと、この詩人は無意識に語っている気がします。
人は、遠くへの憧れとともに、近しい愛を失う運命にあるのかも知れません。そして 、遠くへの旅の中で、自分を捜し、再び永遠なるものをみつけていくのでしょう。
そんな伝統的な象徴詩として、受け止めます。
【編集部より】
初めて読まれる読者に解説させていただきます。「水滴集」は、ミクロコスモスの同人が合作でつくる「秀歌選」「アンソロジー」です。
作者は匿名で参加しますのて、作者を「ミクロコスモス作」として扱っています。俳句、短歌、詩、アフォリズム、きわめて短い小説までが選ばれています。
同人達は、こんな風に、作品に対して、相互に解説や鑑賞と言う形で向き合います。そして、また、少しずつ修正されながら、より完成されたアンソロジーを作っていきます。
丘は三色に染まり、春
レンギョウ、 緋の桃 、豆桜
柔和な土の香、里の丘
あなたが笑顔で
手を振るしぐさ
まっすぐ私をみつめる眼
花によろび
花とあそぶあなた
何もかも今ここにとどまる
こんな近くに丘があり
こんな近くに花があり
こんな近くにあなたがいる
幸せ満ちる一度の春
ふたたび戻らぬ輝きよ
永遠に花咲く里の丘
丘をおとづれる恋人達よ
毎春、われらは美をくりかえす
あたた達は美に向かい、通り過ぎる
いちどの春を過ぎゆく存在を
春を繰り返す存在がよびかける
むせる三色の春のいのち
花は、乙女に言葉を贈る
毎春ごとに美を得る幸せと
遠くへ消えぬ寂しさ語り
こんな近くに丘があり
こんな近くにあなたがいて
こんな近くに春がとどまる
丘は知る 花は知る
愛し合うもの達が
いつか風に、分かれていくことを
だから、消えゆくものへの
思いを光ににつつみ
丘は花を風にゆらす
丘を発ち、わきたつ夏にむかい
異なる街と空を求めて
旅に出るふたり
強い嵐が二人を引き離し
春の輝きはもう遠く
ふたりに、花の言葉は聞こえない
大きな声で呼び合い
過ぎゆく命の実りを得たら
旅の末にもう一度訪れなさい
こんな近くに丘があり
三色の春に輝きがあったことを
私たちが忘れない
こんな近くに花があり
こんな近くに涙して
こんな遠くに愛があり
切断面の響き 「水滴集」より
【読み】 香(か) 三色(みいろ) 永遠 (とわ)
毎春(まいはる)
【解説 1 】
この詩は、三 という数を基底として構成されています。三色の花 「こんな近くに」と言うリフレインをもった部分。3拍をきざむ形は、日本語ではあまり多くありません。
四行詩が、どこか安定感を持つのに対し、三という繰り返し形式は、どこか遠くに進んでいく流れを生み出します。一時の春の花を通り過ぎ、分かれていく運命にある恋人達を語るのに選ばれた形式なのでしょうか。
文頭が一文字下がって書かれいる節は、花の言葉です。詩は、花が恋人達にに語る形式をとってます。
レンギョウ、桃、豆桜 が揃って咲いているのは、関東では見慣れた風景です。そんな三色の花が、少し小高い丘の果樹畑を、たなびくように染めるます。身近で、のどかな風景です。
花の中で、出会い、語り合い、そして見つめる故に分かれていく恋人達。その儚い存在に、花が永遠を語りかけると言う構成で作られています。
「こんな近くに」の部分は、定型詩としてリズムをもって読んでください。情景描写の部分などは、少し破格で語りのリズムで読んでくだい。いずれにしても、声に出して読む事を前提につくられている詩です。
【鑑賞 2 】
恋人達が春の花満開の丘を手を握りあい歩きます。それは喜ばしい風景であるとともに、あやうい儚さも感じさせます。
花は彼らを祝福して語りかけます。でも恋する者には、その声は聞こえません。乙女の視線は、まっすく愛する者に向かい、その近しさの喜びに満たされ、そして「こんな近くに・・」と言う言葉を、たたみ込むように繰り返させます。
「忘れないでいる。」と言うのは、恋する者達どうし、良くささやかれる言葉ですが、その恋人達を、どこかでみつめる、花という存在がどこかにあると詩人は語っているのです。愛の成就には、花と語るやさしさと、永遠と語る強さが必要なのでしょう。
【鑑賞 2 】
思い出します。春の野で、恋人と、歩いた事を。こんな近しい、こんな満たされているとの思いに溢れていました。そして故郷の春は輝いていました。でも、見つめすぎたのかもしれません。やがて、遠くに憧れ、視線がいつしかずれていきました。
今から思えば、花の声を聞くこともなく、その幸せを感謝することもありませんでした。花の声が聞こえないで、人を愛せる筈もないのに。
いつしか、どこか私を包み、受け入れてくれる場所を探す旅に、人生が変わりました。沢山の人と出会い、また別れました。でも、あの春の輝きは見つかりません。
そして、春に故郷に戻り、ふと花咲く風景に会いました。花のもとに行ってみました。なにか、あの人にまた会える気がして。春の光が静かに、花に届いていました。けれど、そんな奇跡はあるはずもありません。
でも、今はこうして、花の声が聞こえるようになりました。木々や、風や、春の光と言葉を交わせるようになりました。永遠に触れた気が少しだけします。今なら、きっと誰かを本当に愛する事が出来る気がします。
【鑑賞 3 】
花が語ると言う思想はロマン主義の伝統です。花は永遠の象徴であると共に、消えゆく実存の象徴でもあります。永遠なる存在と、消えゆく存在の間での語りあいこそ愛の本質なのだと、この詩人は無意識に語っている気がします。
人は、遠くへの憧れとともに、近しい愛を失う運命にあるのかも知れません。そして 、遠くへの旅の中で、自分を捜し、再び永遠なるものをみつけていくのでしょう。
そんな伝統的な象徴詩として、受け止めます。
【編集部より】
初めて読まれる読者に解説させていただきます。「水滴集」は、ミクロコスモスの同人が合作でつくる「秀歌選」「アンソロジー」です。
作者は匿名で参加しますのて、作者を「ミクロコスモス作」として扱っています。俳句、短歌、詩、アフォリズム、きわめて短い小説までが選ばれています。
同人達は、こんな風に、作品に対して、相互に解説や鑑賞と言う形で向き合います。そして、また、少しずつ修正されながら、より完成されたアンソロジーを作っていきます。
桜散る ― 2012/03/27
音楽紹介 「桜散る」さだまさし
みじかいけど、とても好きな言葉があります。
春には春の花が咲き 秋には秋の花が咲き
ふと気がつくと、この言葉を繰り返している時があります。
この言葉だけ取り出せば、
白は白 黄は黄のままに 野の小菊
とりかえられぬ 尊さを咲く
のように実存の美しさを頌える意味にもとれます。
また「日々好日」(毎日が素晴らしい日、それが苦しみの日だとしても)と、捉える事もできます。
そんな難しい意味でもなく、春には春の花が咲いて、のんびりお弁当を食べて、秋には秋の花が咲いて、お団子を食べて・・・と、力を抜いて受けとめても、素敵な言葉です。
でも、この言葉、本当はまったく違う意味なのです。出典はさだまさしの「桜散る」です。
桜散る
言い訳はしないでいいよ わかっているから
愛しすぎる事は多分 愛さないと同じ
いつでも君だけを みつめて生きて来た
春には春の 秋には秋の
それぞれの花が咲く様に
いつか知らず知らず 君と僕の時計
二つの針が時をたがえて
季節が変わる様に 恋が逝く
桜散る 桜散る 雪の面影なぞる様に
桜散る 桜散る もう君が見えないほど
胸をはっておゆき 僕の愛した人
君が愛したものはすべて
僕も同じように愛してきた
今は無理だけれど
いつか年老いたら
君が愛した人を僕も
愛せるそんな日が来るといいね
桜散る 桜散る 思い出を埋めつくして
桜散る 桜散る もう君が見えないほど
桜散る 桜散る 雪の面影なぞる様に
桜散る 桜散る もう君が見えないほど
さだ まさし
そう、恋人との春の別れの言葉なのです。
春には、春の、秋には、秋の、花のように、時を違えてしまった二人が、異なる季節の彼方に行ってしまう・・・
そう言う意味です。言葉の破片は怖いものですね。
何か映画のシーン割りをつけたくなります。
桜並木の端で、二人が最後の言葉を交わし、男は立ち止まり、女性が桜吹雪の中を歩いてく、一度だけ、振り向いて手をふって、そして桜の花の遠くに消えていく・・・・・残るのは真っ白な桜の雲のようにつづく広い風景だけ。
最後に引いて、スパンしてお終いのタイトルが出てきます。
安物映画の作りですが、ほんとうにどこでも繰り返される出来事、安物映画ゆえの真実があるのかも知れません。
こうして、別れた二人なら、きっとしっかりした、道を歩き、いつか「君が愛した人を、僕も愛せる日」が来る」はずです。それは桜が人の想い、人の情念を、吸い取り浄化してくれるからかも知れません。
「桜の木の下には死体が埋まっている」と言ったのはだれでしたか。春の美と、そこに埋められた「死と再生のフォークロア」が、人の情念を浄化して、美しい思い出に変換させてくれるからに違いありません。
春の花に、命のいぶきとともに、ふと寂しい悲しみを感じるのはそのせいでしょう。静かに咲く夜桜は、それを強く漂わせます。
めぐり逢う時は 花びらの中
ほかの誰よりも きれいだったよ
別れいく時も 花びらの中
君は最后まで やさしかつた
つゆのあとさき より
さだ まさし
花は、人をであわせ、人を美しく別れさせます。
「花は、だから美しい。」そう思うと、春の花にいつも涙がこぼれます。
花で別れた二人なら、きっと新しい世界で、新たなる出会いを繰り返して、たくましく生きていく事でしょう。
だから、今、春の花の中をふたりで歩けるのは、最高に幸せな事なんでしょう。・・
次から曲を聴く事ができます。
http://www.youtube.com/watch?v=SCvEYgfyIuU
http://www.youtube.com/watch?v=klPC0tKseTc
みじかいけど、とても好きな言葉があります。
春には春の花が咲き 秋には秋の花が咲き
ふと気がつくと、この言葉を繰り返している時があります。
この言葉だけ取り出せば、
白は白 黄は黄のままに 野の小菊
とりかえられぬ 尊さを咲く
のように実存の美しさを頌える意味にもとれます。
また「日々好日」(毎日が素晴らしい日、それが苦しみの日だとしても)と、捉える事もできます。
そんな難しい意味でもなく、春には春の花が咲いて、のんびりお弁当を食べて、秋には秋の花が咲いて、お団子を食べて・・・と、力を抜いて受けとめても、素敵な言葉です。
でも、この言葉、本当はまったく違う意味なのです。出典はさだまさしの「桜散る」です。
桜散る
言い訳はしないでいいよ わかっているから
愛しすぎる事は多分 愛さないと同じ
いつでも君だけを みつめて生きて来た
春には春の 秋には秋の
それぞれの花が咲く様に
いつか知らず知らず 君と僕の時計
二つの針が時をたがえて
季節が変わる様に 恋が逝く
桜散る 桜散る 雪の面影なぞる様に
桜散る 桜散る もう君が見えないほど
胸をはっておゆき 僕の愛した人
君が愛したものはすべて
僕も同じように愛してきた
今は無理だけれど
いつか年老いたら
君が愛した人を僕も
愛せるそんな日が来るといいね
桜散る 桜散る 思い出を埋めつくして
桜散る 桜散る もう君が見えないほど
桜散る 桜散る 雪の面影なぞる様に
桜散る 桜散る もう君が見えないほど
さだ まさし
そう、恋人との春の別れの言葉なのです。
春には、春の、秋には、秋の、花のように、時を違えてしまった二人が、異なる季節の彼方に行ってしまう・・・
そう言う意味です。言葉の破片は怖いものですね。
何か映画のシーン割りをつけたくなります。
桜並木の端で、二人が最後の言葉を交わし、男は立ち止まり、女性が桜吹雪の中を歩いてく、一度だけ、振り向いて手をふって、そして桜の花の遠くに消えていく・・・・・残るのは真っ白な桜の雲のようにつづく広い風景だけ。
最後に引いて、スパンしてお終いのタイトルが出てきます。
安物映画の作りですが、ほんとうにどこでも繰り返される出来事、安物映画ゆえの真実があるのかも知れません。
こうして、別れた二人なら、きっとしっかりした、道を歩き、いつか「君が愛した人を、僕も愛せる日」が来る」はずです。それは桜が人の想い、人の情念を、吸い取り浄化してくれるからかも知れません。
「桜の木の下には死体が埋まっている」と言ったのはだれでしたか。春の美と、そこに埋められた「死と再生のフォークロア」が、人の情念を浄化して、美しい思い出に変換させてくれるからに違いありません。
春の花に、命のいぶきとともに、ふと寂しい悲しみを感じるのはそのせいでしょう。静かに咲く夜桜は、それを強く漂わせます。
めぐり逢う時は 花びらの中
ほかの誰よりも きれいだったよ
別れいく時も 花びらの中
君は最后まで やさしかつた
つゆのあとさき より
さだ まさし
花は、人をであわせ、人を美しく別れさせます。
「花は、だから美しい。」そう思うと、春の花にいつも涙がこぼれます。
花で別れた二人なら、きっと新しい世界で、新たなる出会いを繰り返して、たくましく生きていく事でしょう。
だから、今、春の花の中をふたりで歩けるのは、最高に幸せな事なんでしょう。・・
次から曲を聴く事ができます。
http://www.youtube.com/watch?v=SCvEYgfyIuU
http://www.youtube.com/watch?v=klPC0tKseTc
凄い ― 2011/09/16
今日の詩
「凄い」
凄い
凄い
凄い
なんだか分からないけど
凄い
凄い
凄い
凄い
どこだか分からないけど
凄い
凄い
凄い
凄い
どうしてだか分からないけど
凄い
凄い
凄い
凄い
どの位か分からないけど
凄い
凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、
凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、
凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、
凄い凄い凄い凄い凄い凄い凄い凄い凄い凄い
凄い凄い凄い凄い凄い凄い凄い凄い凄い凄い
凄い位凄い
凄いところが凄い
凄く凄く凄い・・・
凄いが凄い
凄く凄い・・・
編集長の蛇足
良い文章を書くには、形容詞や副詞を使わないで書くと良い・・と言います。
人を動かすのは、何と言っても事実。いつ、どこで、誰が、どの程度・・それを実態にもとづいた資料をもとに書くのが役に立つ文章。
感動させる・・・それはどうも、良い文章の理念とは違うようです。名詞や動詞は使わないで、「凄い」とか「美しい」とか「とても」とか「真の」とか、修飾語の方が感情に訴えるようです。
その人の書く文章の 「名詞・動詞」対「形容詞・副詞」 の比率を計算したら、「事実度指数」あるいは「空虚度指数」が計測できるかも知れません。
事実度指数の低い人には、余り近づかない方が良いかも知れません。
蛇足の爪の垢
この文章の事実度指数はかなり低くて、あまり読んでも役にたたない種類のものです・・・・
「凄い」
凄い
凄い
凄い
なんだか分からないけど
凄い
凄い
凄い
凄い
どこだか分からないけど
凄い
凄い
凄い
凄い
どうしてだか分からないけど
凄い
凄い
凄い
凄い
どの位か分からないけど
凄い
凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、
凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、
凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、凄い、
凄い凄い凄い凄い凄い凄い凄い凄い凄い凄い
凄い凄い凄い凄い凄い凄い凄い凄い凄い凄い
凄い位凄い
凄いところが凄い
凄く凄く凄い・・・
凄いが凄い
凄く凄い・・・
編集長の蛇足
良い文章を書くには、形容詞や副詞を使わないで書くと良い・・と言います。
人を動かすのは、何と言っても事実。いつ、どこで、誰が、どの程度・・それを実態にもとづいた資料をもとに書くのが役に立つ文章。
感動させる・・・それはどうも、良い文章の理念とは違うようです。名詞や動詞は使わないで、「凄い」とか「美しい」とか「とても」とか「真の」とか、修飾語の方が感情に訴えるようです。
その人の書く文章の 「名詞・動詞」対「形容詞・副詞」 の比率を計算したら、「事実度指数」あるいは「空虚度指数」が計測できるかも知れません。
事実度指数の低い人には、余り近づかない方が良いかも知れません。
蛇足の爪の垢
この文章の事実度指数はかなり低くて、あまり読んでも役にたたない種類のものです・・・・
何者でもないものに ― 2011/07/31
神よ
私を何者でもないもののままにしてください
何か・・専門家と呼ばれず
何か・・何々家と呼ばれる事なく
何か・・何々主義者と呼ばれる事なく
何か・・職業も持たないまま
いつまでも何者であるか分からないまま
いつまでも自分さえ分からないまま
だから誰からも理解される事のないまま
人間であることも忘れられ
生き物である事も忘れられ
存在さえもなくなるような
そんな強く、すがすがしいものにしてください
知っている事はたったひとつ
たったひとつの知恵だけ
不幸と幸せを区別せず
光と影を区別せず
個性ももたず、我もなく
生きている事すら忘れていて
存在さえも忘れている
そんな弱く、限りないものにしてください
きっとあなたからも離れて
存在のない存在として
限りなくたゆとうていくだけ
あ/み
編集長の蛇足
ちょっと分かりにくいかも知れません。この詩・・・というより願いの言葉で言おうとしている事は、あらゆる不幸や憎しみの原因から逃れたいと言う事なのでしょう。
人が不幸になるのは、運命に見えて実は大抵自ら不幸になる原因をつくっている。
幸福になろうとするから、不幸を怖がり、かえって不幸せとなっていく。
自分とは何かを探そうなどとして、自分づくりが苦しみの原因となっていく。
神や思想や信念が、どれほど人を不幸にして、周囲を苦しませるか。
知識を重ねて、重ねるほど、おしゃべりが増えるだけで、本当に語る事ができなくなる。
無・・・ですら、「無」という思想になってしまい、無ですらなくなる。
何々の専門家となると自己保存が始まり、知恵は遠ざかっていく。
何かすがすがしい、何者でもない、存在すら分からないようなそんなものに憧れた作者の心情の吐露の詩なのでしょう。
解説 編集長 森谷
私を何者でもないもののままにしてください
何か・・専門家と呼ばれず
何か・・何々家と呼ばれる事なく
何か・・何々主義者と呼ばれる事なく
何か・・職業も持たないまま
いつまでも何者であるか分からないまま
いつまでも自分さえ分からないまま
だから誰からも理解される事のないまま
人間であることも忘れられ
生き物である事も忘れられ
存在さえもなくなるような
そんな強く、すがすがしいものにしてください
知っている事はたったひとつ
たったひとつの知恵だけ
不幸と幸せを区別せず
光と影を区別せず
個性ももたず、我もなく
生きている事すら忘れていて
存在さえも忘れている
そんな弱く、限りないものにしてください
きっとあなたからも離れて
存在のない存在として
限りなくたゆとうていくだけ
あ/み
編集長の蛇足
ちょっと分かりにくいかも知れません。この詩・・・というより願いの言葉で言おうとしている事は、あらゆる不幸や憎しみの原因から逃れたいと言う事なのでしょう。
人が不幸になるのは、運命に見えて実は大抵自ら不幸になる原因をつくっている。
幸福になろうとするから、不幸を怖がり、かえって不幸せとなっていく。
自分とは何かを探そうなどとして、自分づくりが苦しみの原因となっていく。
神や思想や信念が、どれほど人を不幸にして、周囲を苦しませるか。
知識を重ねて、重ねるほど、おしゃべりが増えるだけで、本当に語る事ができなくなる。
無・・・ですら、「無」という思想になってしまい、無ですらなくなる。
何々の専門家となると自己保存が始まり、知恵は遠ざかっていく。
何かすがすがしい、何者でもない、存在すら分からないようなそんなものに憧れた作者の心情の吐露の詩なのでしょう。
解説 編集長 森谷
優れるという愚かさ ― 2011/04/17
今日の詩
優れるという愚かさ
懸命という狭さ
真理という誤り
善という悪
完璧という不足
天才という欠陥
奥深さというつくりもの
高みという低さ
憎もう 避けよう 疑おう
優れる事を 懸命である事を
真理である事を 善である事を
逃げ尽くして
どこにいくでもなく
そのままでもなく
私
解説
ひとは深い誤りには気付かないようです。身近に転がるあらゆる悪や間違いの原因の原因の原因・・・と突き詰めて行った時に到達する根源の原因が、日頃人々が等しく共通に崇高と信じている価値にある事を。
「国家」、「自由」、「独立」・・・そんな価値に人類は命をかけて多くの犠牲者を出して来た事を歴史は教えてくれます。神という価値に人身御供という犠牲を捧げた歴史は反省できても、未だに平和や平等のために犠牲者を出し続けている事には反省できないようです。
達人、高邁なる人格、一流・・・そんな人達が言葉の最後に呪文のように唱える崇高な到達点こそ、疑い、検証し、深く反省して、その多くを拒否すべきものなのでしょう。そうでないと、人は身近な誤りから永遠に抜け出す事はできません。
編集長の蛇足
達人A 「私は音楽だけに一生を捧げてきました。その結果分かった事は、音楽は平和のためにあると言う事です。」
凡人A 「音楽しかしないで、食べるものは作らなかったの・・・?」
達人B 「私はボールを追い続けて、追い続ける事により、人格が深まった。子供達にも何かを追い続けて、人格を深めてもらいたい。」
凡人B 「球場つくったり、ユニホームつくったり、なんだか、環境破壊しないで、のんびり暮らしたいな・・低人格でも・・」
優れるという愚かさ
懸命という狭さ
真理という誤り
善という悪
完璧という不足
天才という欠陥
奥深さというつくりもの
高みという低さ
憎もう 避けよう 疑おう
優れる事を 懸命である事を
真理である事を 善である事を
逃げ尽くして
どこにいくでもなく
そのままでもなく
私
解説
ひとは深い誤りには気付かないようです。身近に転がるあらゆる悪や間違いの原因の原因の原因・・・と突き詰めて行った時に到達する根源の原因が、日頃人々が等しく共通に崇高と信じている価値にある事を。
「国家」、「自由」、「独立」・・・そんな価値に人類は命をかけて多くの犠牲者を出して来た事を歴史は教えてくれます。神という価値に人身御供という犠牲を捧げた歴史は反省できても、未だに平和や平等のために犠牲者を出し続けている事には反省できないようです。
達人、高邁なる人格、一流・・・そんな人達が言葉の最後に呪文のように唱える崇高な到達点こそ、疑い、検証し、深く反省して、その多くを拒否すべきものなのでしょう。そうでないと、人は身近な誤りから永遠に抜け出す事はできません。
編集長の蛇足
達人A 「私は音楽だけに一生を捧げてきました。その結果分かった事は、音楽は平和のためにあると言う事です。」
凡人A 「音楽しかしないで、食べるものは作らなかったの・・・?」
達人B 「私はボールを追い続けて、追い続ける事により、人格が深まった。子供達にも何かを追い続けて、人格を深めてもらいたい。」
凡人B 「球場つくったり、ユニホームつくったり、なんだか、環境破壊しないで、のんびり暮らしたいな・・低人格でも・・」
まちをつくるのは ― 2011/03/23
今日の詩
まちをつくるのは
そのまちは、風がつくった
おおらかな風は、時に渦巻き、存在をつくる
水を動かし、個性有る大地をつくる
そのまちは、光がつくった
変わらない光は、いのち達の基
だからまちは、清楚な明かりしか持たない
そのまちは、詩人がつくった
風をうたい、光を歌い、大地の個性をうたう
人々が口ずさむのは、大地のうた
解説
「まちづくり」と言う言葉が最近よく使われます。建築家とか、都市計画の専門家が色々な事を言っています。
でも、まちづくりの根底は、詩人の仕事です。詩は未来をつくる言葉です。詩によってつくられたまちが、多分人が愛し続ける事のできるまちに違いないのです。
まちをつくるのは
そのまちは、風がつくった
おおらかな風は、時に渦巻き、存在をつくる
水を動かし、個性有る大地をつくる
そのまちは、光がつくった
変わらない光は、いのち達の基
だからまちは、清楚な明かりしか持たない
そのまちは、詩人がつくった
風をうたい、光を歌い、大地の個性をうたう
人々が口ずさむのは、大地のうた
解説
「まちづくり」と言う言葉が最近よく使われます。建築家とか、都市計画の専門家が色々な事を言っています。
でも、まちづくりの根底は、詩人の仕事です。詩は未来をつくる言葉です。詩によってつくられたまちが、多分人が愛し続ける事のできるまちに違いないのです。
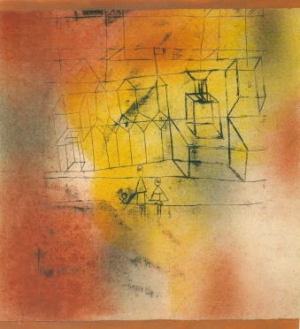
最近のコメント